|
著者紹介
|
|||
 |
北村俊平.元々はモミジイチゴの果実持ち去りパターンをスギ林と広葉樹二次林で比較するつもりでしたが,予備調査で訪れた石川県林業試験場の間伐跡地には,モミジイチゴだけではなく,クサイチゴやクマイチゴも見られました。本論文は急遽,予定を変更して,同所的に生育するキイチゴ属3種の比較調査に取り組んだ結果です。コロナ禍で海外調査が難しいので,最近は自宅の畑でもヒヨドリの吐き戻した種子を集めて発芽実験もしています。 |
||
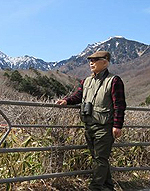 |
山路公紀.北海道生まれ。八ヶ岳南麓に住み,ジョウビタキの繁殖が本州で初めて確認された2010年から調査を継続しています。ジョウビタキはきわめて人に近い環境で繁殖しています。今回は,なぜ換気扇フードが多く利用されるのかを知るため,抱卵する親鳥の視点から解析しました。この鳥は,環境順応性が高いこともあり,林縁に近い住宅地や緑被の多い都市部への繁殖拡大が予想されます。まだ分かっていないことが多いので,解決のために,より多くの方々が研究されることを希望します。 |
||
 |
石井華香.1998年静岡県生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科卒。研究題材を探している際に山路さんの論文に出会い,一緒にジョウビタキの研究をしたいと申し出たのがはじまり。繁殖環境を分析するためにGIS(地理情報システム)を使用したことから,地図づくりを通じて環境分析・環境保全等に貢献したいと思いジオテクノロジーズ株式会社に入社。趣味はスキーで,ジョウビタキが営巣する場所もスキー場周辺が多く,ジョウビタキに親近感を持っています。 |
||
 |
仲村翔太(中)・森荘大郎(左)・三上修(右). <仲村>2000年北海道生まれ。北教大函館校の三上教授の元で鳥類生態学を学び,似ているようで全く違う "ブト" と "ボソ" の魅力に取り憑かれました。現在は白衣に身を包み,道内の高校で理科を教えています。通勤時にたくさんの野鳥を観察できますが,まだまだ知らない鳥ばかり……。今は毎日,授業と鳥類について勉強の日々を送っています。 <森>1999年北海道生まれ。北海道教育大学函館校の三上研究室で鳥類生態学を専攻しました。現在は大学を卒業し,中学校教員として働いています。理科の授業で,在学中に会得したカラスの見分け方を紹介すると,なかなかの盛り上がりでした。これからも鳥類に目を向けながら生活していきたいと思っている今日この頃です。 <三上>まだギリギリ20世紀生まれの学生と研究できています。次は,新世紀生まれの学生と研究をすることになりそうです。写真は卒業式のときのもの。 |
||
| 福田道雄.カワウ標識調査グループ。カワウとは1973年から縁ができ,さまざまな幸運もあって,長く続けられました。そして,それも2019年で一区切りをつけられました。調べ続けることは,それほど苦ではありませんが,それをまとめるのは非常に大変で,ようやく今回の論文にたどりつけました。本調査はカワウにカラーリングを装着し,そのカワウを見つけて知らせてもらうことで成り立ちます。その装着と報告で,ご協力下さった多数の皆様に深く感謝申し上げます。なかでも,積極的に調査に係わって下さりながら,調査期間中に逝去された蓮尾嘉彪氏,戸井田伸一氏,本山裕樹氏,石原由雄氏に改めてお礼を申し上げます。 |
|||
 |
植田睦之.1970年東京都生まれ。2016年から6年間かけて行なった全国鳥類繁殖分布調査,昨年最終報告を出すことができました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。これからは自然保護施策への活用や,様々な研究利用を進めていきたいと思います。まずその第一弾として,今回,分布と温度の関係を示しました。そして同様に長く続けてきたICレコーダのさえずり頻度の記録も論文化できました。 写真は巨木と私。全国鳥類繁殖分布調査では,全国の調査担当者がみつからない調査コースをめぐりました。そんな行きにくいところにはたいがい巨木があります。巨木好きとしてはたまらない調査,そして帰りにカツ丼を食べることで,ついに全都道府県のカツ丼を制覇できました。 |
||
 |
山浦悠一.1976年長野県生まれ。ポスドクをしていた2000年代後半から2010年代の初めまで、全国鳥類繁殖分布調査の解析をしていました。時が経ち、再度全国規模での調査が行なわれ、私は南国高知で暮らしています。先日初めてヤイロチョウの囀りを聞きました!今回の論文は当時に戻ったような内容で、いわゆる「南方系」と言われる種の特徴を示せる有意義なアプローチだと思います。お誘いいただいた植田さんに感謝。 |
||
 |
堀田昌伸.1959年愛知県生まれ。毎春残雪が多く残る時期に,協力者の池田さんとカヤの平に,今年のように林道が閉鎖され往復約26キロを歩くこともありつつも続けてきたI
Cレコーダーの設置が成果になり,植田さんはじめ調査に協力していただいた方々に感謝です。最近は,今回の論文の展開にも関わってくる市民団体との夏鳥の初認・初鳴き調査や,長野県が実施している,ライチョウ目撃情報投稿アプリ「ライポス」で登山者から収集したライチョウ情報の活用に注力しています。また,北アルプス後立山連峰爺ヶ岳や白馬乗鞍岳でライチョウの生息環境調査にも取組むとともに,静岡ライチョウ研究会とともに南アルプス南部上河内岳からイザルガ岳におけるライチョウの生息状況調査も行っています。そろそろ終活せねばと思いつつも,フィールドに出るのが好きで困っています。 |
||
 |
前川侑子.環境アセスメントに関わる仕事につき,猛禽類調査に携わったのをきっかけに,新しい技術を活用した調査の可能性を考えました。人による調査技術も見事なものですが,音声に含まれるたくさんの情報を使って調査ができないか,そう思い技術の開発に至りました。音声×AI技術で,いきもの豊かな自然の保全に貢献できればと思います。研究にご協力いただいたみなさま,いつもありがとうございます。 |
||
 |
松宮裕秋.1994年大阪府生まれ。長野県在住。生まれ育った近畿や現在暮らしている中部地方をフィールドに,人目につかない生き物の「いま」を追っています。クイナ類といえば平野部のヨシ原という先入観があったのですが,山ばかりの紀伊半島の航空写真を眺めているときに,ここならシマクイナがいるのでは?と感じる場所を発見。その予感は当たり,思った以上の越冬を確認しました。今回見つけた場所のいくつかは,既に開発の手が伸びている状況にあり,人知れず生息地が減ることに危機感を覚え,論文化することにしました。これからも目立たない鳥たちの現状を追い続けたいと思っています。 |
||
 |
沼野正博.3月まで和歌山県立高校の教員として勤めながら,県内各地で野鳥の観察を行ってきました。継続して取り組んでいるのは,タカ渡りのカウント。日の岬をフィールドとして,30年近く調査しています。 今回,和歌山県レッドデータブック改定に向けてシマクイナの生息調査を行い,相当数が越冬していることがわかり,急遽「情報不足」として掲載することになりました。すでに県のホームページで公開されています。次回の改定時にはきちんとしたランク付けできるよう,調査を続けていきたいと考えています。 |
||
|
籠島恵介.1963年東京生まれ。現在は仙台在住。ヒクイナはテリトリー争いが激化している場所では実に多様な声を出しますが,整理できていません。調査中に,ヒメクイナ,クイナが反応したこともありました。鳥以外の趣味は筋トレ・自転車・フランスの歴史など。 |
|||
 |
正富欣之.1971年北海道生まれ。2003年からタンチョウに関する研究を始め,2019年に(一社)タンチョウ研究所を設立しました。生息域を拡げたタンチョウを追って,北海道を自動車で走りまわる日々を過ごしています。ネイチャー研究会inむかわの会員として,道央圏における秋期の一斉調査に参加しました。今後のタンチョウ保全にとって,貴重な記録が得られたと思います。これからも同地域における生息地の保全に協力できるように活動していきます。 |
||
 |
小山内恵子.1996年に「ネイチャー研究会inむかわ」が発足し,1998年から会長を務めています。「むかわの自然を次世代に」,次世代を担う子供たちに「遊びを通じて自然体験を」などをテーマとして活動しています。 2011年に道央圏であるむかわ町にやってきたつがいのタンチョウを見守り続け,このつがいは約10年間に8羽のヒナを育てました。2015年に1か月近く育った2羽のヒナがカメラマンに追い回され亡くなってしまう事故が起き,当会はタンチョウのことを多くの方に理解し,積極的に見守るため,「むかわタンチョウ見守り隊」も結成。繁殖期には会議を開き,研修会のほか,営巣地近くのゴミ拾い,秋期の道央圏タンチョウ一斉調査も行っています。 |
||