|
著者紹介
|
|||
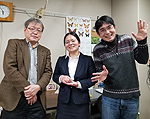 |
立石淑恵・高橋雅雄・東信行.チゴハヤブサは市街地で営巣するため,青森県では町中を歩いていると比較的簡単に姿を見たり,鳴き声を聞いたりできます。その見た目の可愛らしさからバードウォッチャーにも人気の高い鳥ですが,チゴハヤブサの研究例は少ないです。市街地での調査は制限が多く大変でしたが,多くの方々の協力もあり,沢山のデータを収集することが出来ました。今後もチゴハヤブサの生態を明らかにするために,調査に取り組んでいきます。写真は左から東・立石・高橋。 |
||
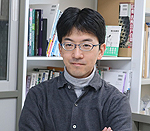 |
三上 修.1974年松江市生まれ。北海道教育大学函館校勤務。もとは,野山の中で鳥を見るのが好きだったのですが,今ではすっかり都市の中の鳥ばかり研究をしています。自由に研究する時間が無くなってしまったので,遠出をせずに手近でできることをやっているというのもありますが,人の作り出した環境と鳥の関係そのものにも興味を持つようにもなりました。というわけで,今回は日本に大量にある電柱電線と鳥の止まり方の関係を調べてみました。データの収集にご協力して下さった皆さん,ありがとうございました。 |
||
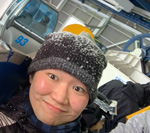 |
廣部博之.1997年北海道生まれ。北海道教育大学函館校卒。三上研究室でスズメやカラスなどの身近な鳥の研究をしていました。私自身,中学生の時からカラスが好きで,現在もあちらこちらのカラスを眺めて過ごしております。大学時代に約1年を通してカラスの研究をできたのは,人生において貴重な経験ができたと思います。カラスの研究および,その他野鳥の研究に携わらせていただいた三上先生に感謝申し上げます。最近の野望,はワタリガラス1日中観察して過ごしたいですね。 |
||
 |
藤岡健人.1996年北海道生まれ。北海道教育大学大学院で,三上先生の下,カラスについて研究していました。はじめ,私にとってカラスは怖い存在でした。しかし,身近にいるカラスが実は2種類いることを知り,興味深い存在に変わりました。今ではすっかりカラスに魅了され,旅行中でもカラスを撮ってしまいます。調査をしていると,雪の中(なかなかの深さ)をのしのし歩いているハシボソを見かけ「なんでわざわざ冷たいところに...かわいい」と,つぶやいていました。写真の撮影場所は北海道美瑛町の青い池です。 |
||
 |
倉沢康大・平田和彦.二人が大学2年生の時に始めたモニタリングの集大成です。目が開かなくなるような吹雪や極寒の中での調査は今となってはいい思い出でです。本来,もっと早く形にすべきところでしたが,当時,卒論・修論とは別に行っていた調査であったこと,お互い社会に出て時間が取れなかったことを言い訳にしたいと思います。なんにせよ,このように形にできたことは大変光栄であり,意義深いものと思っています。気候変動や海洋汚染など,海鳥を取り巻く現状は決して明るいものではありませんが,今回の基礎的なデータが海鳥の保全,ひいては海洋環境の保全の役に立つことを願って止みません。写真左から倉沢,平田。 |
||
 |
佐藤晴香・高島 鼓.北海道教育大学の三上研究室に所属しています。写真にある「鼓晴日和(こはるびより)」とは、私たちのペア名です。高島鼓の「鼓」と佐藤晴香の「晴」からそれぞれとって「小春日和」とかけています。小春日和とは、晩秋から初冬にかけての暖かく穏やかな晴天のこと。そんな天気のように穏やかで暖かく、いままでもこれからも鳥類と関わっていきたいと思っています。愛着がある鳥は、高島鼓は、名前が似ている"ツグミ”、佐藤晴香は今回の研究対象でもある"スズメ”です。 |
||
 |
関 伸一.琉球列島のアカヒゲ研究がライフワーク。アカヒゲのいる島には,同じく島好きのカラスバトやオオミズナギドリも生息することがよくあります。九州と四国の間にある高島にはアカヒゲこそいませんがカラスバトがいて,今回,オオミズナギドリの繁殖も確認されました。私たちはこれまで,高島で増えてしまった特定外来生物のクリハラリスによる生態系への影響と,この外来リスを減らす方法を研究して来ました。外来リスは小鳥の卵を食べますが,オオミズナギドリの卵を食べるかは不明です。しかし,木の実や昆虫も食べる外来リスが減ると,同じ物を食べるネズミ類は増えるかもしれません。ネズミ類は海鳥の繁殖地での捕食者です。島で外来リスが減るとオオミズナギドリにも影響するのか,今,新たな難題に気をもんでいます。写真は高島上陸風景,右が共著の安田,関が撮影。 |
||
 |
植田睦之.1970年東京生まれ。2016年以降,全国鳥類繁殖分布調査が活動の中心でしたが,それも今年で終了しました。たくさんの方のご参加のおかげで,8割できたら上々だな,と思っていたのですが,ほとんどのコースを調査することができました。 その成果報告もかねてユーチューバーデビューもしてみました。これからは,この成果を論文の形でも発表していきたいと思います。 写真はバードリサーチYouTubeチャンネルの画面。繁殖分布の成果報告以外にもいろんなビデオを公開していますので,みてみてください。 バードリサーチYouTubeチャンネル |
||